
|
つくり手の想い・技術がこめられた
|
|
 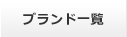 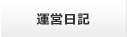  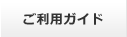  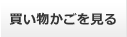
|

|
|
ブランド・作家一覧 |

|
|
ジーンズ・ボトムス |

|
|
Tシャツ・トップス アウター |

|
|
スカート・ワンピース |

|
|
手作り腕時計・懐中時計 |

|
|
手作りアクセサリー |

|
|
財布・がまぐち・革小物 |

|
|
革靴・ブーツ・靴下 |

|
|
バッグ・ストール・ベルト |

|
|
キャンドル・照明 |


|
|
猫・リス・植物・星・和, etc モチーフから選ぶ アクセサリー&腕時計特集 |

|
|
SALEアイテム特集 |

|
|
天然染めアイテム特集 |

|
|
手描き・手染め 和柄Tシャツ |

|
|
倉敷・児島の ジーンズブランド |

|
|
レザーアイテム特集 |

|
|
作り手インタビュー −創作の現場から− |


- graphzero(グラフゼロ)
ジーンズ / トップス / etc.
レディース 
- "禅" 京都発和柄ブランド
ジーンズ / トップス / etc. 
- YoriTo(ヨリート)
ボトムス・トップス 
- 京友禅 丸益西村屋「繭」
Tシャツ / 長袖 / ボトムス 
- 手染メ屋 天然染め工房
半袖/ 長袖/ ボトムス/ etc. 
- 銀工房AramaRoots
シルバーアクセ / 和柄ノ京銀 
- SEED 絵師・杉田扶実子
和柄手描きTシャツ/パーカー 
- saya1003 岩野沙綾香
和柄手描きTシャツ 
- rolca on the notes
ワンピ /トップス /ボトムス
waltz for rolca 
- DEEP BLUE
ボトムス / トップス 
- 備中倉敷工房
ボトムス・トップス 
- "KS" JHA代表・篠原康治
手作り腕時計 
- 渡辺工房
渡辺正明・手作り腕時計 
- "GaTa"watch smith
潟口真功・手作り腕時計 
- cota(コタ)
中野貴臣・手作り腕時計 
- joie infinie design
大護慎太郎・手作り腕時計 
- Mari Goto(マリゴトー)
後藤麻理・手作り腕時計 
- Gothic Laboratory
手作り腕時計 
- ARKRAFT(アークラフト)
新木秀和・手作り腕時計 
- ipsilon(イプシロン)
ヤマダヨウコ・手作り腕時計 
- vie(ヴィー)
手作り腕時計 
- poussette(プセット)
がまぐち / がまぐちバッグ 
- 革工房PARLEY(パーリィー)
レザー製財布・バッグ・小物 
- 達磨(だるま)
革財布・和小物 
- COTOCUL(コトカル)
革財布・革小物 
- garage(ガラージ)
ふわふわ手作りガーゼ服 
- biancabianca 秋澤真衣子
手作りキャンドル 
- nuri candle 福間乃梨子
手作りキャンドル 
- あかりデザイン工房
田畑教次さんの和紙照明 
- ORGANIC GARDEN
オーガニックコットンの靴下 
- IMPROVE MYSELF
革靴・レザーブーツ 
- Dady(ダディ)
レザーベルト・ウォレット 
- ANNAK(アナック)
レザーウォレット・ベルト 
- sasakihitomi 佐々木ひとみ
手作りアクセサリー 
- 二月(ふたつき)
手作りヘアアクセサリー 
- エス 三浦砂織
和柄手作りアクセサリー 
- haru nomura 野村春花
草木染めバッグ・アクセ 
- moge 山口光司
手作りアクセサリー 
- DECOvienya
手作りアクセサリー 
- OHFOREST ユージ大森
手作りアクセサリー 
- Ventriloquist
がまぐちバッグ 
- kobooriza−工房織座−
ストール・マフラー・帽子 
- MOUNTAIN DA CHERRY
倉敷帆布のトートバッグ 
- POUR LA PAIX
ウール素材のバッグ 
- PEARL FISHER
帆布とレザーの手作りバッグ 
- Lano(ラノ)
真鍮と天然石のアクセサリー 
- marship(マーシップ)
動物・植物のアクセサリー 
- 造形作家・コイズミタダシ
コビトのオブジェ・アクセ 
- small right
ミニチュア小物アクセ 
- おりがみトート
舟形トート / リベットトート 
- pure blue japan
ジーンズ / トップス 
- MIZRA(ミズラ)
ボトムス / トップス / etc. 
- mizra(ミズラ)
ジーンズ / トップス 
- mellow out
デザインTシャツ 
- 絵師・冬奇
絵画作品
- ごあいさつ
- ご利用ガイド
- 法律に基づく表記
- ショールームのご案内
- プライバシーポリシー
- メールマガジン登録・変更
- クラフトカフェ楽天市場店
- クラフトカフェYahoo店
- クラフトカフェblog - 運営日記
- 会社概要
- 採用情報
- リンク集


|
クラフトカフェ運営日記 |


|
クラフトカフェWEB本店 |


|
クラフトカフェWEB本店 |


|
クラフトカフェWEB本店 |

|
|
作家・職人・ブランドさんの 募集についてのご案内 |

2017年1月
営業時間:10:00〜18:00 |
|
クラフトカフェ トップ │ 取り扱いブランド一覧 │ 商品・作品カテゴリー一覧 作り手インタビュー 〜創作の現場から〜 一覧 |
| 銀工房AramaRoots(アラマルーツ) シルバーアクセサリー一覧 |
銀工房AramaRoots(アラマルーツ)・ 加藤心姿さん 生み出し続ける挑戦を続けたい。」 |

今回お訪ねした「銀工房AramaRoots(アラマルーツ)」は、2000年に加藤心姿(しんし)さんが立ち上げたアクセサリーブランド。 多彩なアプローチから創作される作品たちは、 長く愛着をもって身につけられるアクセサリーとして多くのファンの心をとらえ続けています。 その工房があるのは、天王山の西に広がる閑静な住宅街の一画。 豊かな自然に恵まれ、数々の歴史の舞台ともなった神秘の地は、 創作へのインスピレーションを育むにふさわしい場所です。 職人気質とともに、多趣味でお茶目な一面も持ち合わせた加藤さんですが、その根底にある、もの作りへの熱い思いが伝わるインタビューとなりました。 |
立体作品を作りたいという欲求をアクセサリーに
|
─もの作りは小さな頃から得意だったんですか。 幼い頃に家族で京都に移り住んだのですが、もともと両親ともに出雲の出身で、祖父は仏像や仏壇をつくる職人でした。 祖父の仕事場の様子や木の匂いは、今もおぼろげに覚えています。その血を親戚で唯一ひいたのが僕だったみたいで、おもちゃの代わりに紙と鉛筆を与えられて、漫画を描いて満足しているような子どもでしたね。 わりと、まわりがびっくりするようなものを創作していました。高校も美術系に進んで、その頃から漫画家になりたいと思い、ずっと描いていました。結局、漫画家は断念したんですが、その後はゲーム会社でキャラクターデザインの仕事をしたり、フリーでグラフィックデザイナーをしたり、趣味でオブジェ的なものを作ってフリーマーケットに出たり…と、さまざまな形で創作にかかわってきました。 ─紆余曲折はあれど、創作ひとすじだったんですね。その終着点がジュエリーデザイナーだった? 30代になったときに、立体的な造形をきちんと仕事になる形で学びたいと考え、働きながら宝飾の専門学校に通い始めました。トシも30を過ぎているし、これからはこれで食べていくんだという思いがあったので、貪欲に学びましたよ。 ─その成果は早々に出たのですね。 まわりにも必死に働きかけたこともあり、ありがたくも友達の紹介などで、早い段階から注文のお声がけをいただくようになりました。 注文を受けてからわからないところは学校で先生に習いながら作るという状態でした。「銀工房AramaRoots」を立ち上げた2000年は、まだ在学中で昼間はサラリーマンでしたが、徐々に注文が増えてきて、なんとかこれ1本にシフトできた感じです。 結局、学校は3〜4年通って覚えるべきことはほぼ覚えてから辞めました。 
─ブランド名「Arama Roots」の由来は? 「私の魂」を意味するアイヌ語「Aram」と「道のり、起源」を意味する英語の造語です。「わが魂の起源」という意味になります。次代のアクセサリーのルーツになれるような魂のこもった作品を、という思いがこめられています。 アイヌ語を使っているのは、当初、アイヌ文様のジュエリーをつくっていこうと思っていたからなんです。でも数作で飽きて、作らなくなってしまった(笑)。 それからは、ハードなメンズ系のシルバーアクセサリー、中にバネを入れて動かしたりする、ギミックで凝ったものなんかを好んで作っていましたね。 ─今とは全然違う作風ですね。 男の子ですから(笑)、やっぱりメカメカしたものやロボットが好きで。しかし労力と価格が釣り合わないという問題がありました(笑)。  
手にする人の喜びが創作へのモチベーション─現在のような女性向けのアクセサリーにシフトされたきっかけは? 百貨店の催事などで販売させてもらう機会が増えてからですね。やはり百貨店という性格上、来てくださるのは女性がほとんどだし、女性メインにしないとブランドとして成長できないと思ったので。 だんだん線を細くして、蝶や花など、自然をテーマにしたものを増やしていきました。 ─テイストの全く違うものを作るのに、抵抗はなかったのですか。 始めはありました(笑)。でも。お客さんとのコミュニケーションの中で喜んでくださる姿を見たり、大切にしていただけることがわかったりすると、やっぱり凄く嬉しくて励みになりました。 それに当時の彼女…今の妻ですが、が、こういうもの、ああいうものという要望を言ってくれるので、なるべく聞くようにして。 
─今では「Arama Roots」の販売やウェブを担われている奥さま!まさに二人三脚は、そこから始まっていたのですね。 そうですね。猫なんかも彼女の要望で作り始めました。僕自身、猫は好きでずっと飼っていたのですが、作品にする気はなかったんです。 こういうリアルで立体的なものは世の中にあふれていたので、自分が作ることに興味がなかったんですね。もともと興味を持っていたのは、複雑なデザインだったから。 でも、10年以上アクセサリーを作ってきた中で、自分らしさを入れていく技術が身についたので、やってみようかと。 ─加藤さんが手がけられる猫の特徴とは? 僕のは、たぶん漫画なんです。実際の猫をモデルにしながら作るのですが、そのままリアルな猫ではなくて、ほんの少し頭と目が大きく、胴が短い。僕なりの愛らしさを入れるというか、かわいいなと思うところを強調しています。 ただ、やりすぎると幼稚になるので、そこはバランスを注意しています。大人の女性のための猫ですね。 



─猫に始まって、今では動物シリーズも広がっていますね。 お客さまのリクエストを聞きながら作っている部分も多いので、犬やうさぎも加わりました。特に犬のリクエストは増えていますね。まだまだ犬を作る作家は少ないので、注目していただいているのではと思います。 ─本当にどの作品も愛らしいですが、作るときはどんなことを心がけていらっしゃいますか。 やはり生き物がモチーフですから、語りかけるような雰囲気を大切にしています。型があがってから一度いぶして、磨きをかけるのが最終工程になるんですが、毛並みの1本1本まで丁寧に、まさに魂を吹き込むつもりで仕上げます。 特に目だけは別に、光るいぶし加工をして、生きているような輝きを宿らせます。だから同じ型でも、できあがると一匹ずつ表情が違うんですよ。うちの子として、愛着をもっていただけたら、作家冥利につきます。   
─それから加藤さんの代表作としてはずせないのが、モルフォ蝶のアクセサリーシリーズですね。最近ではドラマでも使用されて注文が殺到したそうですが。 今は落ち着いています(笑)。これは、イギリスの貴族が好んだアンティークの中にモルフォ蝶の羽をガラスにはさんで宝飾にしたものを見つけて、これを現代の技術でやりたい!と思い研究しました。 材料は、標本に使用できなかったモルフォ蝶の羽ですが、日本では扱っていないのでまずは輸入する方法から調べるなど、一から手探りでした。 ガラスではなく樹脂で再現するにはかなり工夫が必要でしたが、長く樹脂のアクセサリーを作ってきて技術を身につけていたので、巧く加工する技法が編み出せました。他の誰にも真似できないものが作れたと自負しています。 ─樹脂であの美しさをどのように作品化されたかは、企業秘密ですね。 もちろん(笑)。でも、作り始めて5年になるのですが、申し分ないクオリティでできるようになったのは、正直、最近のことです。 その間、なんといっても樹脂など材料のクオリティが格段に進歩しました。今作っているものは完璧に近いです。ですから、以前買っていただいたお客さまのものも、ご要望があれば、材料費だけいただいてメンテナンスをして、ほぼ新品に近い状態に戻します。 モルフォ蝶に限らず、送り出した作品に関しては、すべてメンテを承っています。修理できない素材は使っていないので。 
今欲しいのはジュエリーを自在に彩る技術─作品それぞれに加藤さんのこだわりを凝縮されていることがよくわかります。一作ごとに新しいことにチャレンジされている印象です。 新しい技術を開発したいという思いが常にあって。自分が目指す、憧れとするものを自分なりの形で世の中に出していきたいんですよね。 特に、アクセサリーに色を入れたいとずっと思い続けていて、そんな中でモルフォ蝶にも出会ったのですが、樹脂はやはり永遠不変というわけにはいきません。 色を入れるには、ガラス製のものを組み込んでいくのが一番なんです。すると、たまたま古本屋で見つけた本で、ルネ・ラリックという19〜20世紀に活躍したフランスのジュエリー作家の作品に衝撃を受けました。それから調べれば調べるほどこの技術を自分のものにしたいと思うようになりました。 

僕は手仕事でしか作れないものを作りたい。また、高級なものではなく、ポップで身近だけど安っぽくないものを提供したいと思っているんです。それにぴったりの技法だと思った。日本でいうと原理は七宝の技術と同じなんですが、それだけでは片付けられないものがあります。 ぜひこの技術を取り入れて自分の表現ができるようになりたいのですが、唯一、見つけた学べるところがフランスなんですよ。 ─加藤さんの新境地、早く見たいです。 動くなら今しかないと思っているんですが、なかなか条件が整わなくて。幸い、昔から興味を持ったらまっしぐらという性格なので。まだまだ挑戦する意欲はあります。もう50歳ですから、最後の挑戦としてこの技術を身につけたいと思っています。 


─50歳なんて、まだこれからですよ。でも加藤さんは凄くポジティブですよね。 いや、小さい頃は引っ込み思案で気が弱くて、「どうせ僕なんか」って思ってる子でした。でもあるとき、気がついたんです。こんな考え方じゃダメだ、損ばかりしてる!悪い結果は全部自分で招いているんだって。それにはっきり気づいて、これからは考え方を変えようと思った瞬間を、今でも覚えてるんですよ。小学校にあがる前でした。 ─それはずいぶん早熟な(笑)。 ですかねえ。でもそれから具体的にどう変わったかとか、人生がいい方向に進んで行ったのかとか、そういった記憶は一切ないんです。ただ、考え方として、常に前向きにはなりましたね。 ─人生、どうにかなるって? いや、「どうにかなる」ではどうにもならないです(笑)。ただ、なんとかしなきゃとそれに見合う努力をすることが基本だと思っています。ひと握りの天才は別としてね。 基礎力はとても重要だと思うし、僕はアクセサリーをやろうと思ったときに学校でみっちりと学んだので、時間はかかりましたが今も作家として活動できているのだと思っています。 いろいろまわり道もしましたが、たとえば頭の中で想像したものを立体的に形にできるのは漫画を描いていたおかげだし、努力してやってきたことがすべて、今の自分に役立っています。 ─今後はどのような展開を目指しておられますか。 クラフトカフェさんにご紹介いただいて、異業種でもの作りに携わる人々とのつながりができたのは、本当によい刺激になっています。 みんなどんどん大きくなっていって、凄いなと思うし、ライバルとして意識もする。僕自身、本当に素晴らしい人々とのご縁に恵まれて、ここまでやってこれました。だからこそ、負けてはいられない。 作家ひとりの小さなブランドなのでそんなに手は広げられませんが、ゆくゆくは世界を相手に創作をしたいとも考えています。そのためにも、今の作品にヨーロッパのニュアンスをプラスしたくて、新しい技術を身につけることは必須なんです。 で、ゆくゆくは情熱大陸に出たい(笑)。何よりも自分が納得できて、より多くのお客さまに喜んでいただける作品を作り続けていくことが一番ですね。 ─期待しています。ありがとうございました。 「自分は天才ではなく、普通の人。努力と縁と運だけでここまで来た」と語る加藤さんですが、求められる方向に照準を合わせつつ、作家としてオリジナリティのある作品に昇華する創造力もまた、稀有な才能ではないでしょうか。 柔軟にニーズに応えながらも、作りたいものに挑み続ける「芯」のある創作姿勢は、やはりアーティスト。これからどんな作品が生み出されていくのか、ますます楽しみになりました。 (愛猫のグリとラテュの画像、イタリア・ミラノの展示会の画像は、アラマルーツさんにご提供いただきました) (取材日:2016年5月19日/文:ライター・森本朕世)
銀工房AramaRoots(アラマルーツ) 加藤心姿さん プロフィール
銀工房AramaRoots アイテム一覧
|
|
作り手インタビュー AramaRoots 加藤心姿さん(このページのトップへ) 銀工房AramaRoots(アラマルーツ) シルバーアクセサリー一覧 |
|
クラフトカフェ トップ │ 取り扱いブランド一覧 │ 商品・作品カテゴリー一覧 作り手インタビュー 〜創作の現場から〜 一覧 |
|
トップページ|ご利用ガイド|会社概要|買い物かごを見る|ポイントを確認する|メルマガ登録・変更|ショールームのご案内 Copyright © 2006-2016 有限会社クラフトカフェ All Rights Reserved. |


 作り手インタビュー
作り手インタビュー





